Landing on Water (1986)
ドン・ヘンリーを含む他の1970年代の偉大なアーティストたちが、モダンでシンセサイザーを多用したレコードで80年代にヒットしていたなら、なぜニール・ヤングはそれに挑戦しないのか? この質問に対する明白な答えは、「Landing on Water」のように聞こえるかもしれないからです。この作品では、完璧なまでに良い曲、特に「Hippie Dream」では、David Crosbyが中毒で廃墟と化している様子が壊滅的に描写されていますが、不毛で無感情なプロダクションによって損なわれています。
Everybody’s Rockin’(1983年)
ヤングに「ロック」のアルバムを要求していたレコード会社への記念碑的な中指として、ロカビリーや50年代のR&Bを収録したEverybody’s Rockin’はかなり印象的です。 聴く側としては、そうではありません。
Old Ways (1985)
『My Boy』や『Are There Any More Real Cowboys? 』などの名曲もありますが、ヤングの80年代のカントリーアルバムは、当時のレーベルであるGeffenを困らせるために制作されたと思われますが、過剰に制作され、シロップ漬けで、見下したように聞こえるほど陳腐です。
Are You Passionate? (2002)

好戦的で9.11後をテーマにした『Let’s Roll』で注目を集めたブッカー・T&ザ・MGsとのコラボレーションは、他の点では忘れ去られています。
Peace Trail (2016)
最近のヤングの仕事ぶりや政治的なコミットメントを非難することはできませんが、2016年のセカンド・アルバム『Peace Trail』は、スタンディング・ロック保留地での環境保護抗議活動に触発された部分もありますが、大雑把なソングライティング、オートチューンのボーカルの炸裂を含む中途半端な音楽的アイデア、平凡な歌詞など、めちゃくちゃな内容でした。
Life (1987)
『ランディング・オン・ウォーター』をシンセとドラムマシンの使いまわしで失敗させた後、ヤングは古い仲間であるクレイジー・ホースのアルバムをまったく同じように失敗させました。 Crazy Horseのプリミティブな音楽的アプローチの事実上のマニフェストである『Prisoners of Rock and Roll』で証明されているように、曲はしばしば素晴らしいものだっただけに、これは腹立たしいことだ。 “
Fork in the Road (2009)
「俺は大物ロックスターだけど、売り上げは落ちたよ/でも、まだ君がいるから大丈夫だよ/ありがとう」と、タイトル曲でヤングは言っています。
Broken Arrow (1996)
ヤングの音楽は、長年のプロデューサーであるデビッド・ブリッグスの死後、低迷しているという説が広まっています。彼は、彼を抑制し、インスピレーションに欠けたアイデアを呼び起こすことのできる人物でした。 確かに、ブリッグスの死後に彼が作った最初のアルバムは、クレイジー・ホースの長いジャムと、海賊版のような質の高いライブ・トラックを組み合わせた、広大で方向性のないものでした。
Paradox (2018)
ダリル・ハンナがヤングと彼の最新の若いコラボレーターについて描いた支離滅裂な映画『Promise of the Real』は、1972年の同様に目的のないドキュメンタリー『Journey Through the Past』に匹敵する耐久テストだが、インストゥルメンタル・パッセージ、アウトテイク、ライブ・レコーディングのパッチワークであるサウンドトラックは、かなり没入感があり、漂うように楽しめるが、明らかに熱狂的なヤング・ナッツだけが適用される。
Colorado (2019)
クレイジー・ホースの中途半端なアルバムの最新作である『コロラド』は、バンドのお家芸であるハンストスタイルでの扇情的な演奏が特徴で、『She Showed Me Love』の中盤ではドラマーのラルフ・モリーナが間違って演奏を止めたように見える場面もある。しかし、痛々しいほどに鼻につく政治的な歌詞もあり、まともな曲もあまりない。
Storytone (2014)

優柔不断に悩まされた『STORYTONE』は、オーケストラ付き、ストリップバック、そして両方の要素を取り入れた3つのバージョンでリリースされました。
『Prairie Wind』(2005年)
『Harvest』系統のアルバムの中では最も魅力的ではない『Prairie Wind』だが、ヤングの後期のアルバムの中では強力な部類に入る。 He Was the King」や「This Old Guitar」などの秋めいたムードは、父親の死や、ヤング自身が脳動脈瘤で死と隣り合わせになったことが影響していると思われます。
Silver & Gold (2000)
Harvestのカントリー・ロックの流れを汲むアルバムです。
Greendale (2003)
一部では復調したと評価されていますが、それは単純に前作の『Are You Passionate? – Greendale』はヤングのロック・オペラであり、その壮大なタイトルはラフでブルージーなサウンドとは相反するもののように思われました。 曲作りにもばらつきがあり、興味を持続させることができない。
Arc (1991)
ソニック・ユースのサーストン・ムーアが、ヤングのライブ・パフォーマンスのフィードバックを多用したイントロとアウトロで構成されたライブ・アルバムをリリースすることを提案しました。
The Monsanto Years (2015)
ヤングの最新のバックバンドであるPromise of the Realは、ここでは激しいサウンドを聴かせてくれ、ヤング自身も怒りを露わにしていますが、『The Monsanto Years』は、実際の作曲が見落とされるほど急がされたアルバムのように感じられました。
Trans (1982)
四肢麻痺の息子ベンに触発されたニール・ヤングが、ボコーダー・ボーカルを使った電子的なコンセプト・アルバムを作ったことは、信じられないほど大胆な行動であり、そのためにヤングはよりストレートな曲でこのアルバムを埋め尽くしました。
Hawks & Doves (1980)
家族間の争いに気を取られていたヤングは、名作『Rust Never Sleeps』の次作として、カントリー・チューンや様々なオフ・カットを集めたボロボロのアルバムを発表しました。 ホークス & 「Doves」は不揃いで、タイトル曲はひどくひどいものですが、不吉な「Captain Kennedy」、美しい「Lost in Space」、彼自身のキャリアに対する長い「The Old Homestead」の寓話など、良い部分は素晴らしいものです。
Mirror Ball (1995)
クレイジー・ホースのゆるさと激しさの組み合わせがグランジ・サウンドに重要な影響を与えたことから、「グランジのゴッドファーザー」という肩書きを誇りにしているヤングは、パール・ジャムとコラボレーションした『Mirror Ball』を発表しました。
Chrome Dreams II (2007)
クラシック・ニール:『Chrome Dreams』というアルバムのリリースを断ってから30年後に、その続編を出す。 クロム・ドリームスII』は、18分という驚異的な『Ordinary People』という1曲に集約されています。

Americana (2012)
『Clementine』や『Oh Susanna』など、フォークソングを劇的に再構築したアルバム『Americana』は、散発的に素晴らしく、時にだらしなく、時に純粋に驚くような作品です。
Neil Young (1968)
「オーバーダブ・シティ」とヤングはソロ・デビューの時に抗議しましたが、それは的を射ていました。 The Loner」、「Here We Are in the Years」、「The Old Laughing Lady」など、ヤングがライブで繰り返し演奏することになる素晴らしい曲が満載ですが、ジャック・ニッチェの凝ったアレンジの重さにしばし唸ってしまいました。
Psychedelic Pill (2012)
クレイジー・ホースは、長時間のジャムを演奏することで有名になりましたが、Psychedelic Pillはそのアプローチを極限まで高めました。
Dead Man (1995)
ヤングの最初の映画サウンドトラックである1972年の『Journey Through the Past』は、ライブ録音とアウトテイクの寄せ集めで、『Harvest』の後続作品だと思っていたファンを恐怖に陥れることに成功した作品です。 ジム・ジャームッシュ監督の超現実的な西部劇「Dead Man」のラフカットに合わせてライブ演奏されたこの曲は、長大で荒涼とした、時に暴力的なギターインストゥルメンタルという別のものです。
American Stars ‘N Bars (1977)
ヤングの1970年代のスタジオ・アルバムの中で最も弱い作品である『American Stars ‘N Bars』は、当時未発表だった『Homegrown』から取られたトラックと、ローファイなホーム・レコーディング(奇妙に不気味な『Will to Love』)、鉛のようなカントリー・ロック、そして紛れもないクレイジー・ホースの名曲1曲を組み合わせたものです。
A Letter Home (2014)
ジャック・ホワイトが所有していた1947年製のレコード録音ブースでヤングがカバー・バージョンを録音するというのは斬新に聞こえますが、バート・ヤンシュの「Needle of Death」など、ヤングがコーヒーハウスのフォーク・シンガーとして演奏していたであろう曲から、ブルース・スプリングスティーンの「My Hometown」の心に響くバージョンまで、「A Letter Home」はうまく機能しています。
『Living With War』(2006年)
100人の聖歌隊をバックに、迅速にレコーディング、リリースされた反イラク戦争をテーマにした『Living With War』は、自分の仕事の緊急性と、それが引き起こすであろう騒動を知っていたであろうヤングのエネルギーに満ちたサウンドです。 この曲を多用した後のクロスビー・スティルス・ナッシュ&・ヤングのツアーは、より保守的なファンからのブーイングや退出によって迎えられました。
『Re-ac-tor』(1981年)
ヤングの息子が受けた過酷な治療プログラムに影響を受けているため、意図的にそうしているクレイジー・ホースのアルバム『Re-ac-tor』は、ハードワークであり、時に刺激的ではなく、『Surfer Joe』や『Moe the Sleaze』の猛烈な騒音や『Shots』の締めくくりのように、時に素晴らしいものです。
Harvest (1972)
『Harvest』の商業的大成功が、ヤングの意地っ張りな、逆張りの行動のきっかけになったことは、それほど不可解なことではありませんでした。 曲は素晴らしいものから(タイトル曲や『Words』)、忘れられがちなものまで様々で、アレンジは洗練されていますが、『A Man Needs a Maid』のように大げさなものもあります。
This Note’s for You (1988)
ヤングの80年代のジャンル実験の中で最も成功した作品であり、クリエイティブな再生を果たした、ブルージーなR&Bアルバムは、タイトル曲で最もよく知られており、80年代のロックが企業スポンサーに傾倒していたことを非難していますが、その最高の瞬間は繊細で控えめです。
HIPHOPは、80年代のロックにありがちな企業のスポンサーシップを批判したタイトル曲で知られています。
Hitchhiker (1976)
デヴィッド・ブリッグスが言うように、ヤングが一人でスタジオに入って「蛇口をひねって」新曲を流した音です(結局ほとんどの曲が別の場所で再録音されました)。
Le Noise (2010)
ダニエル・ラノワがプロデュースしたこのアルバムは、ヤングの21世紀最高のアルバムであり、彼を新たな場所に連れて行ってくれました。 ラノワが時折、混乱を招くようなテープループを加える一方で、ヤングは耳をつんざくような音量で明らかに歪んだエレクトリック・ギターを演奏して自身を伴奏しています。
Harvest Moon (1992)
Harvest Moonは、そのタイトルが参照しているクラシック・アルバムや、そのバック・ミュージシャンを再構成したアルバムよりも優れています。 そのサウンドは、切なくてノスタルジーを帯びた曲に合っています。 タイトル曲は、Everly BrothersのWalk Right Backからリフを引用したもので、結婚と不朽の愛への純粋に美しい賛美歌です。
Ragged Glory (1991)
クレイジー・ホースの最も原始的な姿は、ヤングが馬糞の山の中に立ってボーカルを録音したというもので、ガレージ・ロックのスタンダード曲(プレミアーズの「Farmer John」)、暴れ回るジャム曲(「Love and Only Love」、「Mansion on the Hill」)、そして自分たちの限界への賛歌(「F!#*in’ Up」)で大暴れします。
Homegrown (1975)
俳優のキャリー・スノードグラスとの別れをきっかけに録音してから45年、2020年に遅れてリリースされた『Homegrown』について、ヤングは「人生には傷つくこともある」と説明しています。
Comes a Time (1978)
レコード会社が『Harvest』の次に出したかったであろう穏やかなカントリー・ロック・アルバム『Comes a Time』は、その精神的な前作よりもはるかに優れています。
Freedom (1989)
混乱していた1980年代の後、ヤングは完全な怒りのパワーを取り戻し、彼が影響を与えたグランジ・ムーブメントの初期に合わせて完璧なタイミングでリリースされました。 広く誤解された「ロッキン・イン・ザ・フリー・ワールド」がヒットしましたが、「フリーダム」には、ホーンが効いた長い「クライム・イン・ザ・シティ」(Sixty to Zero)や、フィードバックが効いた猛烈な「オン・ブロードウェイ」のカバーなど、キラー・トラックが満載です。
Sleeps With Angels (1994)
カート・コバーンの遺書にはヤングの歌詞が引用されていましたが、作者はそれに恐怖を感じていました。 他の部分では、70年代半ばの作品と同様に、荒涼とした説得力と不気味さがあり、Crazy Horseは驚くほど控えめな演奏をしています。
Time Fades Away (1973)
商業的にブレイクしたニール・ヤングが、悲惨なツアーの混乱したオーディオ・ベリテの記念品を出すのはニール・ヤングだけです。 しかし、『タイム・フェイズ・アウェイ』は、単なる「お詫びの品」ではなく、非常に魅力的な作品です。 ラストダンス」のヒッピーのような激しい音、壊れやすいピアノバラード「The Bridge」、自伝的な「Don’t Be Denied」などの曲は信じられないほど素晴らしく、ぼろぼろになった演奏によってさらに引き立てられています。
『Zuma』(1975年)
『Time Fades Away』、『Tonight’s the Night』、『On the Beach』の「溝の三部作」に比べて軽快なトーンの『Zuma』は、ヤングと活性化したクレイジー・ホースとの再会を果たし、『Barstool Blues』の酔っぱらった心の彷徨いの見事な表現や、陰鬱で荘厳な歴史大作『Cortez the Killer』を生み出しました。 そして、この作品の最後を飾る『Through My Sails』は、クロスビー・スティルス・ナッシュ&・ヤングが発表した最後の真の名曲となっています。
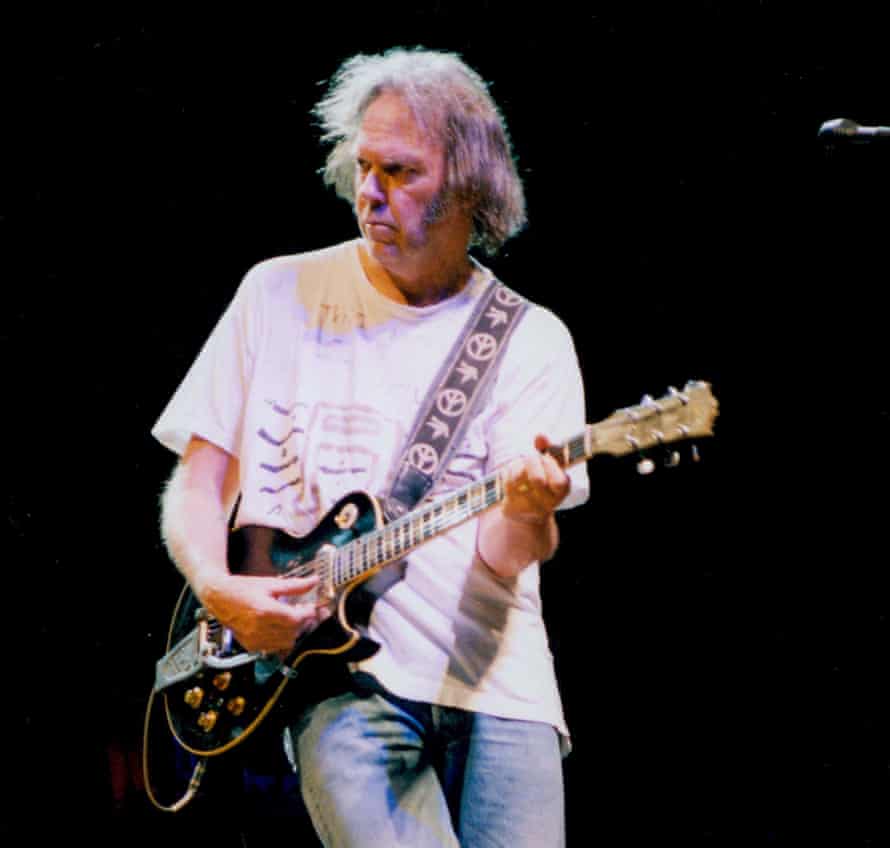
After the Gold Rush (1970)
『After The Gold Rush』は、ヤングの60年代の翌朝のアルバムのように感じられますが、サイモン&
On the Beach (1974)
絶望と落胆に満ちた曲ですが、美しい音楽に彩られています。「See the Sky About to Rain」のきらめくエレクトリック・ピアノ、壮大なアコースティック・クローザーの「Ambulance Blues」(「You’re all just pissing in the wind」と締めくくられています)、タイトル・トラックのストンとした霧のようなロックの表現。
Tonight’s the Night (1975)
クレイジー・ホースのギタリスト、ダニー・ウィッテンとローディーのブルース・ベリーの死に対するヤングのテキーラ漬け、フィルターなしの反応は、悲惨で、非常にパワフルな聴きものであり、演奏中の酔っぱらった騒々しさと曲の生の感情がマッチしています。 Mellow My Mind」でのヤングの声の割れ方は、おそらく彼のカタログの中で最も強烈なものでしょう。
Everybody Knows This Is Nowhere (1969)
ヤングのクレイジー・ホースでのデビュー作は素晴らしいアルバムです。曲とサウンドの力強さ、Cinnamon Girlのキラー・リフ、Down By the RiverとCowgirl in the Sandの拡張ジャムでの演奏は、歌詞の怒りを体現しており、10分を超えても聴き手を完全に魅了し続けます。
Rust Never Sleeps (1979)
ヤングのライブ・アルバムとスタジオ・アルバムの境界線は、常に柔軟なものです。 RUST NEVER SLEEPS』は、1978年にステージ上で録音され、その後オーバーダビングされたものです。 しかし、『RUST NEVER SLEEPS』は、彼の素晴らしさのすべてを完璧にまとめ上げている。そのクオリティは、『Hey Hey, My My (Into the Black)』や『Thrasher』で彼が言及したパンク・ムーブメントが拍車をかけているのかもしれない。 サイド1のアコースティックな曲の連続は息を呑むような美しさで、サイド2ではクレイジー・ホースが雷のようなスタイルで怒りを爆発させ、Powderfingerの暴力、死、家族の絆を描いた悲痛な物語は、間違いなく彼の最高傑作と言えるでしょう。